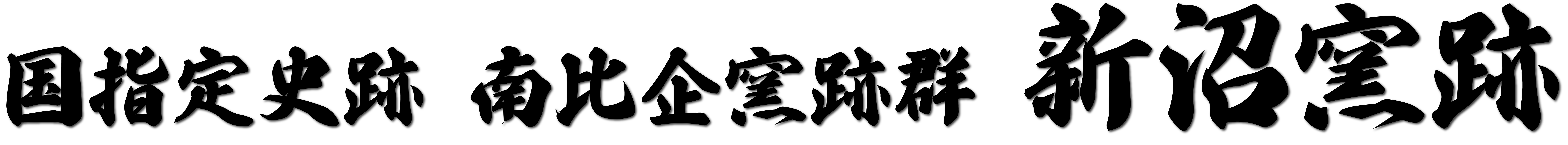国指定史跡 南比企窯跡群 新沼窯跡のご紹介
南比企窯跡群とは?
南比企窯跡群(みなみひきようせきぐん)とは、埼玉家比企郡鳩山町を中心に嵐山町やときがわ町など比企南丘陵分布する須恵器や瓦を生産していた窯跡の総称です。
6世紀初めに鳩山町に隣接する自治体である東松山市の高坂地区で須恵器の生産を開始しました。
そして、鳩山町には良質な粘土があったこともあり、7世紀後半には鳩山町の石田遺跡や赤沼古代瓦窯跡などで瓦や須恵器を生産するようになりました。その後、8世紀中期には新沼窯跡が武蔵国分寺創建期の瓦を生産しました。これらの鳩山町にあった窯跡群を総称して鳩山窯跡群(はとやまようせきぐん)と呼んでいます。
しかし、9世紀には鳩山町での生産が衰退、その後は嵐山町やときがわ町など現在の近隣の自治体にて生産されるようになりました。
現在の鳩山町には"須江"という地区があります。この地区名の由来は須恵器から来ているともいわれており、いかに鳩山町で須恵器・瓦を生産していたかを物語っているといえるのではないでしょうか?
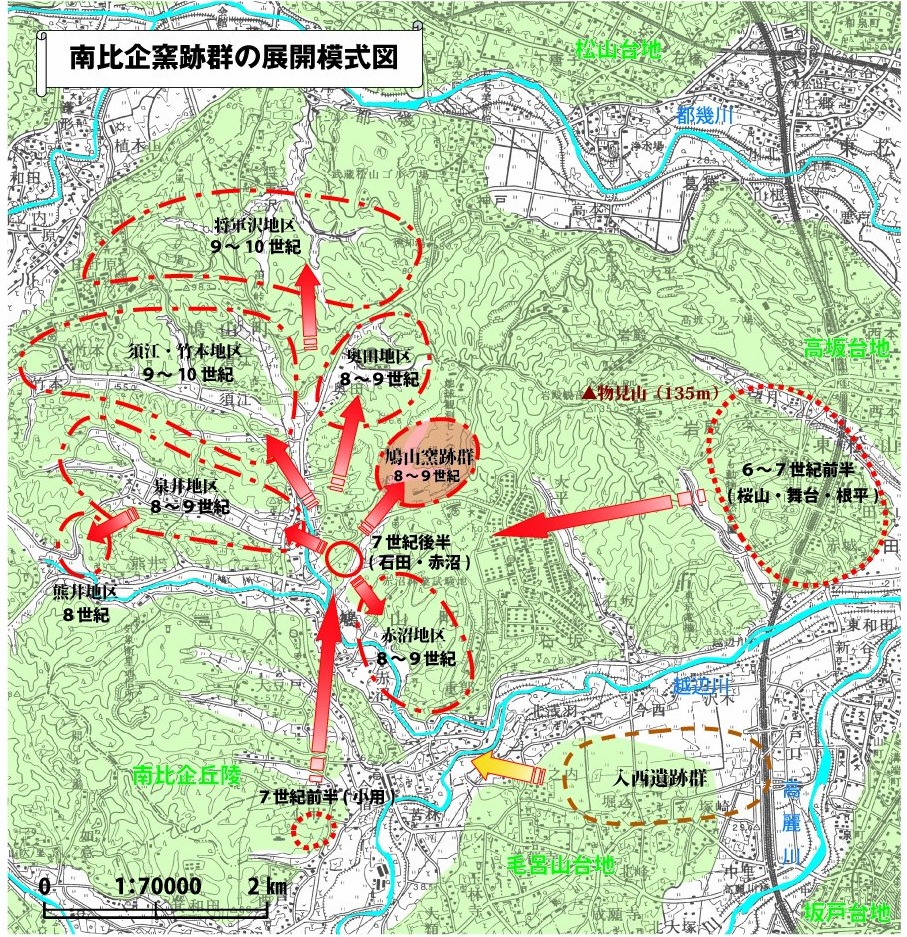
画像は鳩山町HPから
新沼(しんぬま)窯跡の誕生
奈良時代の天平年間は災害や藤原広嗣の乱といった反乱が起こり、天然痘などの疫病するなど、社会不安が高まっている時代でした。そんな時代に天皇だったのが、大仏や正倉院で有名な聖武天皇です。
聖武天皇は、このような不安な状況を脱するべく仏教に帰依し、遷都を繰り返していきます。
そのなかで聖武天皇は、仏教により国を守るという思想である鎮護国家思想の下で天平13年(741年)には国分寺建立の詔を、天平15年(743年)には大仏建立の詔を発したのです。
国分寺建立の詔では、国分寺は当時の日本の各国におかれることとなり、設置する場所の選定が行われました。結果的に、現在の埼玉県や東京都である武蔵国の国分寺は東京都国分寺市に置かれることが決定されます。
そして、武蔵国分寺で使う瓦を生産する場所として選ばれたのが、鳩山町泉井の新沼だったのです。
新沼窯跡における瓦・須恵器の生産
新沼窯跡には26基という日本最大規模の窯が置かれ、奈良時代の8世紀中期から後期までにかけて武蔵国分寺向けの瓦を生産しました。
そして、生産した瓦は40Kmほど離れた国分寺まで運ばれて行きました。
なお、9世紀ごろの須恵器も出土しているため、この時期にも生産を行っていたと考えられています。
奈良時代の生産品は須恵器、瓦、瓦塔(がとう)、平安時代の生産品は須恵器でした。また、出土した瓦には当時の群の名前が記された群名瓦があったことが知られています。
新沼窯跡の発掘調査
鳩山における窯の衰退以降、新沼窯跡も使われなくなりましたが、長い時間を経て江戸時代に発見され、昭和34年(1959年)に立正大学考古学研究室による本格的な発掘調査が行われました。
新沼窯跡からは武蔵国分寺の瓦が多く発掘されたことから、学会では有名な存在となります。
そして平成23年(2011年)、鳩山町教育委員会により窯跡群の保存を目的に発掘調査が再び行われました。調査では大量の瓦が出土し、一般的な瓦をはじめとして軒平瓦や軒丸瓦などの様々な瓦が出土しています。
それだけでなく、象徴的な瓦とされる鬼瓦が出土しました。そのため、新沼窯跡は武蔵国分寺の瓦生産において重要な役割を持っていたと考えられています。
その後の南比企窯跡群 新沼窯跡
令和4年(2022年)12月16日、新沼窯跡が含まれる南比企窯跡群が国の文化審議会文化財分科会の審議・議決を経て、国史跡へ指定するように文部科学大臣に答申されます。
これにより、奈良時代の貴重な史料を出土した新沼窯跡が国指定史跡に指定されることになったのです。
新沼窯跡の見学について
新沼窯跡は私有地にあるため、今日に至るまでイベントを除き一般公開をしておりません。
特に最近は地権者の高齢化により環境の維持作業が困難になっており、安全に見学ができる状態となっておりません。そのため、今後も新沼窯跡を公開する予定はありませんし、無断で見学された場合も安全の保障ができません。
ですが、学術目的などで見学を希望される場合は地権者および鳩山町教育委員会にご連絡をいただければ一時的に公開することも考えておりますので、こちらからご連絡ください。
新沼窯跡自体は公開しておりませんが、鳩山町が出土品や写真の展示を行っておりますので、そちらの見学を行うこともお勧めします。